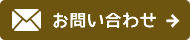昔も現在も根強い人気をほこる柴犬。さまざまな犬種の中でも、比較的長生きすることが特徴でもあり、病気にも強いとされています。しかし柴犬にも、かかりやすい病気は存在します。少ないですがしっかりチェックしましょう。
-アトピー性皮膚炎
犬の皮膚に関する病気はさまざまですが、アトピー性皮膚炎は、柴犬が最もかかりやすい病気です。
発症時期は3歳未満が多いですが、3歳を超えてから発症するケースも少なからずあります。
アトピー性皮膚炎は、アレルギー(免疫グロブリン)となる食べ物やほこり、花粉・ダニといったものを吸い込んでしまうことにより起こる病気です。
・症状
アトピー性皮膚炎にかかった場合、皮膚のかゆみ・赤み・フケ・脱毛といった症状があらわれます。
かゆみが強くなると、柴犬は身体をかきむしってしまい、皮膚に傷ができたり、膿んでしまったりします。
基本的にアトピー性皮膚炎は、身体全体のどこでも起こります。
特に多く発症する部位として、脇の下周辺・お腹周りがあげられます。
また目の周りや耳周り、肉球の間や足の付け根に発症する場合もあります。
・治療法
アトピー性皮膚炎の完治は難しいとされています。
そのため主な治療法は「対処療法」になります。
アレルギー物質は血液検査によって特定することができ、アレルギー源に応じて食事内容の見直しやほこり、花粉の除去といったことを行います。
かゆみの症状に対しては抗ヒスタミン剤やステロイド系の炎症薬などを用います。
・予防法
予防法は、身体を清潔にすることです。
汚れていることで細菌が発生しやすくなるため、それに伴いかゆみも強くなります。
したがって、定期的にシャンプーやブラッシングを行い、できる限り柴犬の身体を清潔に保ちましょう。
なお、薬用シャンプーや保湿剤を合わせて使用すると、より効果的な予防が可能です。
-認知症(痴呆症)
柴犬は犬の中でも比較的寿命が長く、平均して15歳くらいまで生きます。
しかしその一方で長生きする分、認知症に発症する確率も高くなってしまいます。
特に柴犬は、11歳を超えたあたりから認知症になる確率が一気に上がってしまうのです。
・症状
認知症と一口に言っても症状はさまざまです。
柴犬においての症状で最も多いのが、夜中に鳴きだす「夜鳴き」といわれています。
日中は寝ているので特に問題はありませんが、夜中になると鳴きだすことで、飼い主だけでなく近隣の方たちにも迷惑がおよんでしまうことが現状です。
夜鳴きは普段聞き慣れている鳴き声よりも大きく、一定の間隔で鳴くことが特徴です。
もう一つの症状として、認知能力の低下があります。
食べたことを忘れてしまうので食事量が増える、場所を選ばずに排泄をしてしまう、などといった特徴が見られます。
また、飼い主とその家族、自分が住んでいる家の場所すらわからなくなってしまう場合も多いようです。
・治療法
認知症の治療は、薬物やサプリメントを使用して行います。
また認知症に有効といわれている、DHAやEPAを含んだ食事を、病院で処方してもらうこともできます。
・予防法
効果的な認知症の予防法としては脳に刺激を与えることが挙げられます。
たとえば室内で飼っているのであれば、できる限り外に連れ出すことです。
室内だけの場合、刺激が足りずに認知症を加速させてしまう可能性があります。
また散歩に関しても、たまにはいつもと違ったコースにしてみるなど、柴犬の脳に刺激を与えてあげましょう。
また、スキンシップを多く行うことも脳への刺激となり、認知症を防いでくれます。
柴犬の顔を見ながら話をしたり、身体をマッサージしてあげましょう。
-股関節形成不全(こかんせつけいせいふぜん)
体と後ろ足を支える股関節のゆるみ・変形がおこることにより、その痛みで柴犬が体を支えきれずに歩けなくなってしまう病気です。
先天性による発症がほとんどですが、後天性で発症するケースも少なからずあります。
しかし、早めに病院にて治療を受けることで、完治が可能です。
・症状
主な症状は、歩く際にお尻を大きく左右に振って歩く、走る時に後ろ足を揃えたまま走る、立つ・座るといった動作を嫌がるといった特徴が見られます。
・治療法と予防法
症状の重さによって変わってきますが、主に投薬治療や手術を行います。
予防法としては、症状が重くならないように安静にしつつ、肥満体とならぬよう、食事内容に気をつけることが重要です。
-膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)
膝蓋骨脱臼は、膝のお皿の骨が脱臼してしまう病気であり、先天性の要因によって発症するケースが多い病気ともいわれています。
・症状
脱臼による痛みで、後ろ足をかばって引きずるように歩いたり、さわると痛がったりするといったことが見られます。
特に足を引きずっている場合は、膝蓋骨脱臼が悪化しているため、後ろ足を全く使えなくなっています。
また3本足で歩く場合もありますから、症状を進行させないように注意が必要です。
・治療法
膝蓋骨脱臼の主な治療法は、投薬によって痛みを抑える・または手術です。
一般的には、膝蓋骨脱臼と判明した時点で手術をすることが望ましいとされています。
そのため、上記のような症状があらわれた場合、すぐに病院に連れていってあげましょう。
・予防法
予防法として、できる限り足に負担をかけないように心がけることです。
まず、高い場所から飛び降りる行為は決してさせてはいけません。
また階段を昇り降りする際にも、足に少なからず衝撃があります。
そのため絨毯(じゅうたん)やカーペットなどで、足への衝撃をできる限り少なくなるようにしてあげましょう。
-白内障
白内障とは、目の水晶体が白くにごり、視力がいちじるしく悪くなってしまう目の病気です。
主に10歳以上の老犬に多くみられます。
一方、若い犬であっても、若年性や外傷を負うことにより白内障を発症する場合もあるようです。
そして白内障は最悪の場合、失明してしまう可能性がある病気でもあります。
・特徴
白内障の大きな特徴は、目が白く濁ることです。
しかしもともとは、目は黒いですから、すぐに気づきます。
他には、以前とは違う行動がみられます。
主に物にぶつかりやすくなる・こちらと目が合わなくなる・表情が乏しくなる、といったことです。
また、目がみえないことから、不安そうにするという特徴も見られます。
・治療法と予防法
白内障の主な治療法として、目薬・内服薬・手術があげられます。
しかし残念ながら目薬および内服薬は、白内障の進行を抑えることしかできません。
現状、白内障を治療するためには、手術以外に方法がないようです。
したがって、目が白く濁っているのを発見次第、病院に連れていってあげることが最も有効といえるでしょう。
白内障はほとんどの場合において、加齢によって発症します。
そのため有効な予防法はありません。
飼い主ができる予防法は、できる限り紫外線を避け、目の色を定期的にチェックし、早期発見を心がけることです。
また、白内障の引き金となる目のケガ・糖尿病にならないように努めることも怠ってはいけません。
-まとめ
柴犬は病気に強いことは説明しましたが、命にかかわる病気にかかる可能性もあるのです。
また病気の症状によっては、飼い主だけではなく、周りに迷惑がおよぶ場合もあります。
そのため基本的なことではありますが、早期発見、早期治療を心がけましょう。